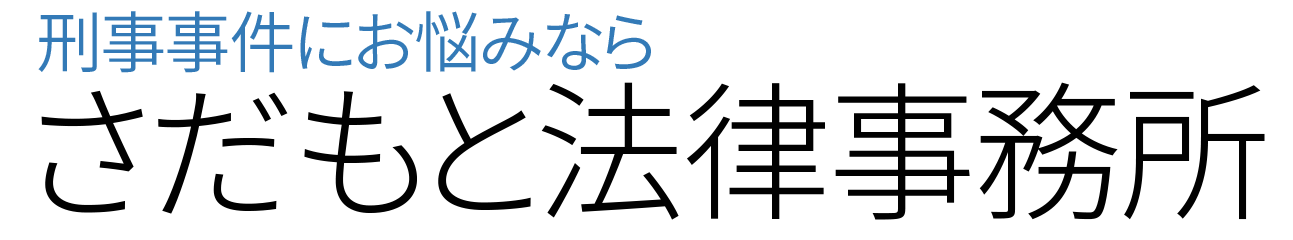カルロス・ゴーンの発言から日本の刑事裁判を考える
ゴーン被告人の発言
保釈許可条件を破って違法に出国したカルロス・ゴーン被告人が、日本の刑事裁判の場で闘わなかった理由を、「日本の司法制度の異端さを断固としてはっきりさせるためにここにいる」とし、「日本でも、この時代遅れの司法制度と非人道的な人質司法と戦ってくれました。これはフェアではない、根本的な市民の自由、そして国際的な規範に違反するものです。」としています。
日本法の適用のある者が、日本の司法制度・裁判制度の外で、争そおうということは、日本法を否定するものであり許されることではないと思います。
しかし、ゴーン被告人が指摘する日本の刑事司法の問題は、残念ながら事実であると言わざるを得ません。少なくとも、被疑者・被告人のために弁護活動をする弁護士は皆そう思っていると思います。
人質司法
まず、「人質司法」です。
「人質司法」とは、法律の条文にある言葉ではありません。
日本の犯罪捜査・刑事裁判の現状が、逮捕・勾留されると、「自白をしなければ勾留が続き、自白をしなければ保釈も検察の反対により認められない。出してほしければ自白しろ、保釈になりたければ争うのをやめてすべて認めろ」との強引な取り調べが行われ、「延々と勾留を続けるのは裁判所だから「人質司法」と呼ばれる。」のです(「無罪請負人 刑事弁護とは何か」弘中惇一郎 著」)。
近時は、勾留を取り消したり、勾留の延長(逮捕後、裁判所の1回目の勾留決定の期間は10日で、起訴前には原則1度だけ勾留期間の延長が10日の範囲で認められる)を認めなかったり、保釈が認められる場合も、少しずつ増えてきてはいますが、それでも、自白しなければ、まず、勾留・勾留延長・保釈申請不許可になります。自白させるために、身体の自由を「人質」にしているという現実は厳然と存在しています。
罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがなければ勾留決定をすることができず、保釈を許可しないといけないのですが、裁判所・検察官は、およそこのようなことが具体的に考えられなくても、認めません。被告人は、当事者として、国家権力と闘っていかないといけないのに、拘束されている状況では何もできません。拘束のない自由な状態で証拠を集め、裁判で無罪を争うのが原則です。日本の刑事裁判は、原則と例外が逆転しているといわなければなりません。
刑事手続きの国際基準
次に「国際的な規範」です。
日本は、2013年5月に、国連拷問禁止委員会に「取り調べに弁護人の立ち会いがないと、誤った自白が行われるのではないか。自白に頼り過ぎる取り調べは中世の名残だ。日本の刑事手続きを国際水準に合わせる必要がある。」と指摘されていますが、取り調べに弁護士が立ち会うことは法律上は認められていませんし、人質司法によって、自白偏重の取り調べがまだ行われています。この点についてのゴーン被告人の指摘も正しいといわざるをえません。
日本国憲法は「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く拘留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることはできない」「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」として、自白の偏重を否定しています。自白以外の客観的証拠があるかどうかで、犯罪の成否を決めるべきなのです。
日本の問題は「規範」(ルールの取り決め)の問題ではなく、法を適用する最判所・運用する検察官の意識に問題があるのです。
私達弁護士ができること、しなければならないこと
私達、弁護士は、日本国憲法のこの原則を強く主張し、人質司法の問題点を指摘して、勾留についての争い、保釈許可に向けての努力を地道に続けて行き、裁判官の意識を変えさせていくように、頑張って行かないといけないのです。